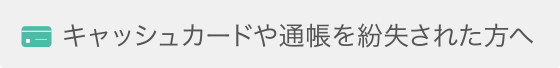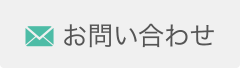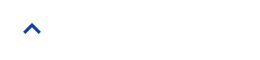採用情報詳細
募集要項
3月13日(金)会社説明会開催のご案内
2027年3月卒業の学生を対象に会社説明会を開催いたします。
どのような組織で、どのような業務をしているのか知って頂くための説明会です。
当日は若手職員との交流会や会内見学も実施予定です。
学生の皆さんのご参加をお待ちしております!
お申込・詳細はマイナビ2027の本会ページをご覧ください。
マイナビ主催合同説明会(3月1日)に参加します!
選考で活かせる情報が一気に掴める!
本会では、マイナビが主催する『就職セミナー』に参加します。
是非ご来場ください!当会ブースにてお待ちしております!
| 日時 | 令和8年3月1日(日)13時~17時 |
|---|---|
| 場所 | アイメッセ山梨 https://job.mynavi.jp/conts/event/2027/10339/index.html |